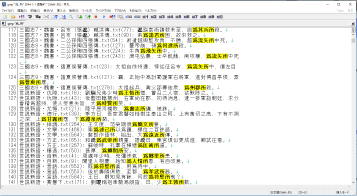『捕蛇者説』「募有能捕之者」の「有」の意味は?
- 2019/05/26 22:38
- カテゴリー:漢文の語法
(内容:柳宗元「捕蛇者説」に見られる「募有能捕之者、当其租入」の句の「有」の意味について考察する。)
先日、勉強熱心な若い同僚が教科書を持って質問に来られました。
この表現がよくわからないので教えてほしいと示された箇所を見て、「あ、しまった…」と慌ててしまいました。
其始太医以王命聚之、歳賦其二。募有能捕之者、当其租入。
いうまでもなく柳宗元の『捕蛇者説』の一節で、問題は後半の「募有能捕之者」の部分です。
教科書では「能く之を捕ふること有る者を募りて、其の租入に当つ。」と読まれています。
同僚の疑問は、本文が「募能捕之者」ではなく「募有能捕之者」となっている「有」の意味でした。
私がこの質問に慌てたのは、ずっと以前にある教科書会社の教師用指導書に説明をつけていて同じ疑問を抱いたのに、その時解決できずに先送りをしてしまった苦い思い出があったからです。
その時はどう調べてもわからなかったのですが、さらに調べ続けようという努力をしなかった、それが今になって若い人に質問されて答えられないという失態を招いてしまったわけです。
明確に答えようがなくとも、せめて私見だけでも述べられるようにもっと調べるべきだったと恥ずかしく思いました。
正直に「わからない」と答えはしたものの、もちろんそのままにしておくわけにはいきません。
まず教師用指導書を見てみました。
すると、次のように訳してあります。
(それで州では)その蛇を捕まえることができた者を見つけ出し、(その蛇を納めることで)その者の(本来納めるべき)租税の代わりとした。
しかし、「募有能捕之者」の箇所だけ、語注がありません。
「募」を「見つけ出し」と意訳したところがいかにも怪しげですが、「捕まえることができる者」ではなく、「できた者」と訳してあるところに、おそらく教科書を執筆した高等学校の先生の「有」への疑問が透けて見えるような気がしました。
そこで今度は別の指導書を見ると、次のように訳してあります。
(そこで永州では)この蛇を捕まえることのできる者を募集して、その者の税の代わりとした。
これだと「募有能捕之者」ではなく「募能捕之者」の訳になるわけですが、この指導書にもこの箇所だけ語注がありません。
「有」に対する疑問を感じなかったか、あるいは私と同様、解決がつかないのであえて触れられていないのでしょうか。
そこで、この手の指導書が参照した可能性の高い参考書をあたってみることにしました。
まずは『新釈漢文大系71・唐宋八大家読本 二』(明治書院1976)です。
募りて能く之を捕らふる者有れば、其の租入に當つ。
(州では人を募って、この蛇を捕らえることができた者があれば、その租税のかわりとしたので、)
語注はありませんが、訓読が異なります。
なるほどこのように読めば、「有」の説明はつくわけですね。
先の指導書にあった「できた」はこのあたりが元かもしれません。
次に『研究資料漢文学6・文』(明治書院1993)です。
能く之を捕らふる有る者を募りて、其の租入に当つ。
((永州では、)この蛇を捕らえることができる人を募集して、(蛇を)その人の租税の代わりにする(ことができる)ようにした。)
「募有能捕之者」ではなく「募能捕之者」の訳ですね。
この書にも語注や解説はありません。
続いて『漢詩・漢文解釈講座・第14巻・文章Ⅱ』(昌平社1995)。
能く之を捕らふる有る者を募りて、其の租入に当つ。
((そこでこの州では)蛇を上手につかまえる者を募り、その者の税の代わりとした。)
「募能捕之者」の訳になりますが、「能」を「上手に~する」と訳しています。
この書も語注や解説はありません。
困ったことに、手元にある有名どころの解説書がみな説明なしにスルーです。
いったいどういうことでしょうか。
そこで手元に唯一あった中国の訳本を見てみることにしました。
招募能够捕蛇的人,用捕来的蛇抵偿他们应交纳的租税,…(『柳宗元哲学著作注译』范阳主编 广西人民出版社1985)
(蛇を捕まえることができる人を募って,捕まえてきた蛇で納めなければならない租税の代償とした,…)
この1冊だけではなんとも言えませんが、日本の解釈と変わりません。
前回行き詰まったのも、同じ過程を踏んだ結果です。
さて、どうしたものでしょうか。
ここで問題を整理してみたいと思います。
本文がもし「募能捕之者」であれば、施事主語「永州」、謂語「募」(募集する)で、その賓語が「能捕之者」(これを捕まえることができるもの)で、語法的には何ら問題はありません。
ところが、「募有能捕之者」となっているために、「有」の処理に困ってしまうわけです。
通常、動詞「有」が「者」字結構を伴って、「~するもの(こと・ひと…)がある(いる)」という存在文を構成することが多いのは周知のことです。
だからどうしても「有能捕之者」は、「これを捕まえることができる人がいる」という意味になってしまう。
ところが、「募」が全体の謂語となっているために、構造的には「有能捕之者」がその賓語になり、名詞句として「これを捕まえることができる人がいること」と解せざるを得ない。
つまり「これを捕まえることができる人がいることを募る」という極めて違和感のある解釈になってしまうのです。
これなら「有」がない方が明らかに自然な表現になります。
『新釈漢文大系』が先に「募りて」と読んでいるのは、「有能捕之者」を「募」の直接の賓語とするのを避けて違和感を解消するためなのでしょう。
結局恥ずかしながら私的には前回「能く之を捕らふること有る者を募りて」と訓読しました。
やはりこれは「有~者」の構造ではなく、「者」字結構全体が「募」の賓語とみなす方がよいのではと思い試みた訓読でした。
あるいは「能有りて之を捕らふる者を募りて」と読んだ方がいいかとも考えたのですが、確証が得られませんでした。
「有」という動詞は、客観的な存在を表す動詞ですが、なぜ、わざわざここに「有」を用いる必要があったのか。
あるいは衍字か?とも考えました。
しかし、そのような指摘は見られません。
そこで、「募有」の例を検索にかけてみることにしました。
ここでは便宜的に「有」の意味についてはぼかした形で試しに訳をつけてみます。
・募有能入城為諜者、騎士馬景請行。(資治通鑑・唐紀七十九)
(敵城に入って間諜の仕事ができるものを募ると、騎士の馬景が行くことを求めた。)
・福王与芮素恨似道、募有能殺似道者使送之貶所、有県尉鄭虎臣欣然請行。(宋史・姦臣列伝四)
(福王、与芮はもともと似道を怨んでいて、似道を殺すことができるもので彼を貶所に送らせる者を募ると、ある鄭虎臣という県尉が喜んで行くことを求めた。)
以上の例の場合、「有」を存在の意でとるとどうしても不自然な解釈になり、「有」のもう一つの義である「具有」の意で解釈して「能力があって~する人」ととれば、意味は一応通ります。
・請召募有罪亡命之人充軍。(元史・兵志一)
(罪があって亡命している人を募って軍の兵にあてることを求めた。)
たとえばこの例の場合、「有罪」はやはり二字で意味をなしていると考えるべきでしょう。
問題は「有能」をこれと同じだと解釈できるか、つまり「能」が「能力」という名詞であって可能の助動詞ではないと考えてよいかです。
この説が成立すれば、「能有り之を捕ふる者を募りて」と読んで、「能力があり蛇を捕まえるものを募り」と解釈することができますが、さてどうでしょうか。
『史記・商君列伝』に次のような例があります。
・恐民之不信、已乃立三丈之木於国都市南門、募民有能徙置北門者予十金。
(人民が信じないことを心配して、やがて三丈の木を国都の市の南門に立て、人民に北門に移し置くことができるものがあれば十金を与えると募った。)
「募」以下の部分の成分をどう考えるかという問題はあるのですが、仮に「募民有能徙置北門者」でも文は成立します。
この「民有能徙置北門者」を存在文ではないと考えることは相当無理があります。
やはり存在主語「民」+謂語「有」+賓語「能徙置北門者」とみなすべきでしょう。
そうだとすれば、やはり「人民に北門に移し置くことができるものがいる」という意味にならざるを得ません。
少なくとも「民の能有り北門に徙し置く者」という意味ではないでしょう。
それなら、連詞「而」を加えるとか、何らかの処理が必要になるような気がします。
そう考えていくと、先の「募有能入城為諜者」にしても、「募兵有能入城為諜者」と表現できるはずです。
確かに違和感はあるのですが、「兵の中に敵城に入って間諜の仕事ができるものがいるのを募る」という、適任の客観的な存在を募るという解釈も、あながち無理ではないようにも思えてきます。
そうだとすれば、「募有能捕之者」は、「能く之を捕らふる者有るを募りて」と読み、「(人民に)これを捕まえることができるものがいるのを募集して」と解釈することになり、「能く之を捕らふること有る者を募りて」という訓は妥当ではないことになります。
しかし、まだどうにも納得がいきません、違和感が払拭できないからです。
「募有」の例を、さらにもう少し見てみましょう。
・募有得之者当授相位。(太平広記・宝三)
(これを見つけだすものがいれば宰相の位を授けるだろうと募った。)
・募有降者厚賞之。(資治通鑑・唐紀六)
(降すものがいればこれに厚く賞を与えると募った。)
・募有能出戦者賞之。(宋史450・忠義列伝五)
(出て戦うことができるものがいいればこれに賞を与えると募った。)
おもしろいことに気づきます。
「有~者」がいずれも条件節になっていて、前句で述べる~の存在を条件に、どうするかという結果を後文で示す、いわゆる複文の構造になっています。
どうやら見えてきました。
つまり、「募」の賓語は前句「有~者」だけではなく、後句も含めた内容と考えられるわけです。
たとえば後者の例の場合、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能出戦者→(複文後句結果)賞之」
(謂語「募る」+賓語「出て戦うことができる人がいれば→これに賞を与える」と)
の構造だというわけです。
このような見方で、前の違和感のあった例文を見直してみましょう。
・募有能入城為諜者、騎士馬景請行。
この文も実は複文の後句が示されていないだけではないでしょうか。
つまり、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能入城為諜者→(複文後句結果)…」
(謂語「募る」+賓語「敵城に入って間諜の仕事ができる人がいれば→(どうする)」と)
「敵城に入って間諜の仕事ができる人がいれば」と募集した結果、騎士の馬景が行くことを求めた。
・福王与芮素恨似道、募有能殺似道者使送之貶所、有県尉鄭虎臣欣然請行。
この例も先の解釈は誤っていて、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能殺似道者→(複文後句結果)使送之貶所」
(謂語「募る」+賓語「似道を殺すことができるものがいれば→彼(=似道)を貶所に送らせる」と)
その募集の結果、ある鄭虎臣という県尉が喜んで行くことを求めた。
要するに「募有」の文の構造は、
賓語「募」+賓語「(複文前句条件)有~者→(複文後句結果)…」
(謂語「募る」+賓語「~するものがいれば→どうする」と)
の形で説明できるというわけです。
さて、それでは柳宗元の『捕蛇者説』の場合はどうでしょうか。
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能捕蛇者→(複文後句結果)当其租入」
(謂語「募る」+賓語「蛇を捕まえることができるものがいれば→その人の租税の納入にあてる」と)
きちんと説明ができました。
つまり、「募有能捕之者、当其租入。」は「『蛇を捕まえることができるものがいればその人の租税の納入にあてる』と募った」という意味、したがって本文は「能く之を捕らふる者有れば其の租入に当つと募る。」と読むのがよいのではないでしょうか。
だからこそ、永州の人は毒蛇を探しに奔走することになるのです。
先日、勉強熱心な若い同僚が教科書を持って質問に来られました。
この表現がよくわからないので教えてほしいと示された箇所を見て、「あ、しまった…」と慌ててしまいました。
其始太医以王命聚之、歳賦其二。募有能捕之者、当其租入。
いうまでもなく柳宗元の『捕蛇者説』の一節で、問題は後半の「募有能捕之者」の部分です。
教科書では「能く之を捕ふること有る者を募りて、其の租入に当つ。」と読まれています。
同僚の疑問は、本文が「募能捕之者」ではなく「募有能捕之者」となっている「有」の意味でした。
私がこの質問に慌てたのは、ずっと以前にある教科書会社の教師用指導書に説明をつけていて同じ疑問を抱いたのに、その時解決できずに先送りをしてしまった苦い思い出があったからです。
その時はどう調べてもわからなかったのですが、さらに調べ続けようという努力をしなかった、それが今になって若い人に質問されて答えられないという失態を招いてしまったわけです。
明確に答えようがなくとも、せめて私見だけでも述べられるようにもっと調べるべきだったと恥ずかしく思いました。
正直に「わからない」と答えはしたものの、もちろんそのままにしておくわけにはいきません。
まず教師用指導書を見てみました。
すると、次のように訳してあります。
(それで州では)その蛇を捕まえることができた者を見つけ出し、(その蛇を納めることで)その者の(本来納めるべき)租税の代わりとした。
しかし、「募有能捕之者」の箇所だけ、語注がありません。
「募」を「見つけ出し」と意訳したところがいかにも怪しげですが、「捕まえることができる者」ではなく、「できた者」と訳してあるところに、おそらく教科書を執筆した高等学校の先生の「有」への疑問が透けて見えるような気がしました。
そこで今度は別の指導書を見ると、次のように訳してあります。
(そこで永州では)この蛇を捕まえることのできる者を募集して、その者の税の代わりとした。
これだと「募有能捕之者」ではなく「募能捕之者」の訳になるわけですが、この指導書にもこの箇所だけ語注がありません。
「有」に対する疑問を感じなかったか、あるいは私と同様、解決がつかないのであえて触れられていないのでしょうか。
そこで、この手の指導書が参照した可能性の高い参考書をあたってみることにしました。
まずは『新釈漢文大系71・唐宋八大家読本 二』(明治書院1976)です。
募りて能く之を捕らふる者有れば、其の租入に當つ。
(州では人を募って、この蛇を捕らえることができた者があれば、その租税のかわりとしたので、)
語注はありませんが、訓読が異なります。
なるほどこのように読めば、「有」の説明はつくわけですね。
先の指導書にあった「できた」はこのあたりが元かもしれません。
次に『研究資料漢文学6・文』(明治書院1993)です。
能く之を捕らふる有る者を募りて、其の租入に当つ。
((永州では、)この蛇を捕らえることができる人を募集して、(蛇を)その人の租税の代わりにする(ことができる)ようにした。)
「募有能捕之者」ではなく「募能捕之者」の訳ですね。
この書にも語注や解説はありません。
続いて『漢詩・漢文解釈講座・第14巻・文章Ⅱ』(昌平社1995)。
能く之を捕らふる有る者を募りて、其の租入に当つ。
((そこでこの州では)蛇を上手につかまえる者を募り、その者の税の代わりとした。)
「募能捕之者」の訳になりますが、「能」を「上手に~する」と訳しています。
この書も語注や解説はありません。
困ったことに、手元にある有名どころの解説書がみな説明なしにスルーです。
いったいどういうことでしょうか。
そこで手元に唯一あった中国の訳本を見てみることにしました。
招募能够捕蛇的人,用捕来的蛇抵偿他们应交纳的租税,…(『柳宗元哲学著作注译』范阳主编 广西人民出版社1985)
(蛇を捕まえることができる人を募って,捕まえてきた蛇で納めなければならない租税の代償とした,…)
この1冊だけではなんとも言えませんが、日本の解釈と変わりません。
前回行き詰まったのも、同じ過程を踏んだ結果です。
さて、どうしたものでしょうか。
ここで問題を整理してみたいと思います。
本文がもし「募能捕之者」であれば、施事主語「永州」、謂語「募」(募集する)で、その賓語が「能捕之者」(これを捕まえることができるもの)で、語法的には何ら問題はありません。
ところが、「募有能捕之者」となっているために、「有」の処理に困ってしまうわけです。
通常、動詞「有」が「者」字結構を伴って、「~するもの(こと・ひと…)がある(いる)」という存在文を構成することが多いのは周知のことです。
だからどうしても「有能捕之者」は、「これを捕まえることができる人がいる」という意味になってしまう。
ところが、「募」が全体の謂語となっているために、構造的には「有能捕之者」がその賓語になり、名詞句として「これを捕まえることができる人がいること」と解せざるを得ない。
つまり「これを捕まえることができる人がいることを募る」という極めて違和感のある解釈になってしまうのです。
これなら「有」がない方が明らかに自然な表現になります。
『新釈漢文大系』が先に「募りて」と読んでいるのは、「有能捕之者」を「募」の直接の賓語とするのを避けて違和感を解消するためなのでしょう。
結局恥ずかしながら私的には前回「能く之を捕らふること有る者を募りて」と訓読しました。
やはりこれは「有~者」の構造ではなく、「者」字結構全体が「募」の賓語とみなす方がよいのではと思い試みた訓読でした。
あるいは「能有りて之を捕らふる者を募りて」と読んだ方がいいかとも考えたのですが、確証が得られませんでした。
「有」という動詞は、客観的な存在を表す動詞ですが、なぜ、わざわざここに「有」を用いる必要があったのか。
あるいは衍字か?とも考えました。
しかし、そのような指摘は見られません。
そこで、「募有」の例を検索にかけてみることにしました。
ここでは便宜的に「有」の意味についてはぼかした形で試しに訳をつけてみます。
・募有能入城為諜者、騎士馬景請行。(資治通鑑・唐紀七十九)
(敵城に入って間諜の仕事ができるものを募ると、騎士の馬景が行くことを求めた。)
・福王与芮素恨似道、募有能殺似道者使送之貶所、有県尉鄭虎臣欣然請行。(宋史・姦臣列伝四)
(福王、与芮はもともと似道を怨んでいて、似道を殺すことができるもので彼を貶所に送らせる者を募ると、ある鄭虎臣という県尉が喜んで行くことを求めた。)
以上の例の場合、「有」を存在の意でとるとどうしても不自然な解釈になり、「有」のもう一つの義である「具有」の意で解釈して「能力があって~する人」ととれば、意味は一応通ります。
・請召募有罪亡命之人充軍。(元史・兵志一)
(罪があって亡命している人を募って軍の兵にあてることを求めた。)
たとえばこの例の場合、「有罪」はやはり二字で意味をなしていると考えるべきでしょう。
問題は「有能」をこれと同じだと解釈できるか、つまり「能」が「能力」という名詞であって可能の助動詞ではないと考えてよいかです。
この説が成立すれば、「能有り之を捕ふる者を募りて」と読んで、「能力があり蛇を捕まえるものを募り」と解釈することができますが、さてどうでしょうか。
『史記・商君列伝』に次のような例があります。
・恐民之不信、已乃立三丈之木於国都市南門、募民有能徙置北門者予十金。
(人民が信じないことを心配して、やがて三丈の木を国都の市の南門に立て、人民に北門に移し置くことができるものがあれば十金を与えると募った。)
「募」以下の部分の成分をどう考えるかという問題はあるのですが、仮に「募民有能徙置北門者」でも文は成立します。
この「民有能徙置北門者」を存在文ではないと考えることは相当無理があります。
やはり存在主語「民」+謂語「有」+賓語「能徙置北門者」とみなすべきでしょう。
そうだとすれば、やはり「人民に北門に移し置くことができるものがいる」という意味にならざるを得ません。
少なくとも「民の能有り北門に徙し置く者」という意味ではないでしょう。
それなら、連詞「而」を加えるとか、何らかの処理が必要になるような気がします。
そう考えていくと、先の「募有能入城為諜者」にしても、「募兵有能入城為諜者」と表現できるはずです。
確かに違和感はあるのですが、「兵の中に敵城に入って間諜の仕事ができるものがいるのを募る」という、適任の客観的な存在を募るという解釈も、あながち無理ではないようにも思えてきます。
そうだとすれば、「募有能捕之者」は、「能く之を捕らふる者有るを募りて」と読み、「(人民に)これを捕まえることができるものがいるのを募集して」と解釈することになり、「能く之を捕らふること有る者を募りて」という訓は妥当ではないことになります。
しかし、まだどうにも納得がいきません、違和感が払拭できないからです。
「募有」の例を、さらにもう少し見てみましょう。
・募有得之者当授相位。(太平広記・宝三)
(これを見つけだすものがいれば宰相の位を授けるだろうと募った。)
・募有降者厚賞之。(資治通鑑・唐紀六)
(降すものがいればこれに厚く賞を与えると募った。)
・募有能出戦者賞之。(宋史450・忠義列伝五)
(出て戦うことができるものがいいればこれに賞を与えると募った。)
おもしろいことに気づきます。
「有~者」がいずれも条件節になっていて、前句で述べる~の存在を条件に、どうするかという結果を後文で示す、いわゆる複文の構造になっています。
どうやら見えてきました。
つまり、「募」の賓語は前句「有~者」だけではなく、後句も含めた内容と考えられるわけです。
たとえば後者の例の場合、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能出戦者→(複文後句結果)賞之」
(謂語「募る」+賓語「出て戦うことができる人がいれば→これに賞を与える」と)
の構造だというわけです。
このような見方で、前の違和感のあった例文を見直してみましょう。
・募有能入城為諜者、騎士馬景請行。
この文も実は複文の後句が示されていないだけではないでしょうか。
つまり、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能入城為諜者→(複文後句結果)…」
(謂語「募る」+賓語「敵城に入って間諜の仕事ができる人がいれば→(どうする)」と)
「敵城に入って間諜の仕事ができる人がいれば」と募集した結果、騎士の馬景が行くことを求めた。
・福王与芮素恨似道、募有能殺似道者使送之貶所、有県尉鄭虎臣欣然請行。
この例も先の解釈は誤っていて、
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能殺似道者→(複文後句結果)使送之貶所」
(謂語「募る」+賓語「似道を殺すことができるものがいれば→彼(=似道)を貶所に送らせる」と)
その募集の結果、ある鄭虎臣という県尉が喜んで行くことを求めた。
要するに「募有」の文の構造は、
賓語「募」+賓語「(複文前句条件)有~者→(複文後句結果)…」
(謂語「募る」+賓語「~するものがいれば→どうする」と)
の形で説明できるというわけです。
さて、それでは柳宗元の『捕蛇者説』の場合はどうでしょうか。
謂語「募」+賓語「(複文前句条件)有能捕蛇者→(複文後句結果)当其租入」
(謂語「募る」+賓語「蛇を捕まえることができるものがいれば→その人の租税の納入にあてる」と)
きちんと説明ができました。
つまり、「募有能捕之者、当其租入。」は「『蛇を捕まえることができるものがいればその人の租税の納入にあてる』と募った」という意味、したがって本文は「能く之を捕らふる者有れば其の租入に当つと募る。」と読むのがよいのではないでしょうか。
だからこそ、永州の人は毒蛇を探しに奔走することになるのです。