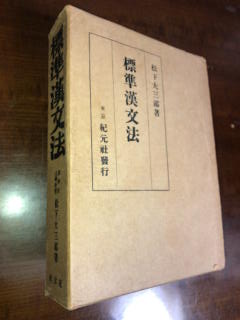「莫――者」について
- 2020/07/31 18:24
- カテゴリー:漢文の語法
(内容:無指代詞と呼ばれる「莫」が「者」を伴う構造について考察する。)
SNSなどというものとは縁の遠い生活をしておりまして、ツイッターというものも利用したことがないのですが、たまたま「莫」について調べていると、S氏のツイートを拝見することができました。
S氏は、ずいぶん前にネット上で知り合うことのできた方で、漢文に造詣が深く、仕事の上でもお世話になったことがあります。
そのまま引用するのは憚られますので、端折って載せますと、
「無・莫・勿・毋」は体言を否定するという漢文解説を見たが、「無」はまだしも、「莫」は本当に体言を否定するのか?
というものでした。
「『無・莫・勿・毋』は体言を否定する」という説明がもしなされているのだとしたら、S氏ならずとも驚いてしまいますが、S氏の「『無』はまだしも、『莫』は本当に体言を否定するのか?」という言葉にこめられた意図は、おそらく「無人」のように、「無」の後に体言が置かれることはあっても、「莫人」のように体言が置かれることなどあるのか?ということだと思います。
「無」は「有」の対義で、「~を無す」(=~が存在しない)を肯定的に述べる動詞で、「無人」なら、「人を無す」(=人がいない)という事実を肯定的に判断して述べるものです。
したがって、「無人」は否定文ではなく肯定文になるわけですが、それはともかくとしても、「人」という体言(の存在)を否定していると、言えば言えないこともありません。
ですが、「莫」は中国の語法学では無指代詞(指すもののない代詞)とされ、いわば英語の「nobody」「nothing」に相当すると言われていますから、主語として用いられて、「莫A」の形をとるなら、Aは動詞、もしくは動詞のように働いている語でなければなりません。
つまり、「莫A」は、「存在しないものがAする」から「誰もAしない」または「何ものもAしない」という意味を表すとされるわけです。
「莫」を無指代詞とすることについては、本当にそれが妥当であるかどうか、さらに考える必要はあると思いますが、S氏の「『莫』は本当に体言を否定するのか?」という疑いは、今の説明からも当然のことになります。
ところが、S氏は、さらにツイートされていて、
「莫――者」という表現があることを確認した。しかし用例はわずかで標準的な表現とは言えず、受験に必要な知識ではない。
という旨のことを述べられました。
この時、私は「あれ?」と思ったのです。
「用例がわずか」で「標準的な表現とは言えない」が、気になりました。
S氏が「莫――者」の用例を確認されたのは、「――者」が名詞句になるからでしょう。
「――者」は名詞句ではあっても、体言ではないのですから、そこまでこだわられなくてもいいと思うのですが、ひっかかるところがおありだったのでしょうか。
私が「あれ?」と思ったのは、「莫――者」という表現が結構よく出てくるという認識をもっていたからです。
拙著を改訂していて、「莫」の用法については、多くの用例にあたっていますが、よく目にするような気がします。
試しに自前のデータのgrep検索で「莫.*者。」の例を探してみると、たちまち何百例もヒットしました。
「莫.*者、」やその他の検索を加えれば、相当数にのぼるでしょう。
もちろん単純にこの文字列にヒットした数ですから、一つひとつ吟味すれば除外されるものも多く含まれていると思いますが、「用例がわずか」とはとてもいえません。
・自制河以東、蒼梧已北、莫不厭若魚者。(荘子・外物)
((捕らえた魚のあまりの大きさに、)制河から以東、蒼梧山から以北は、だれもこの魚に食べ飽きないものはいなかった。)
・女倚柱而嘯、旁人聞之、莫不為之惨者。(列女伝・仁智)
(むすめが柱にもたれて口笛を吹くと、そばにいる人はそれを聞き、だれもこの悲しげな音色に痛ましく思わない者はなかった。)
・群臣莫敢諫者。(劉向新序・刺奢)
(群臣たちは諫めようとするものはいなかった。)
古い例をいくつか拾い上げてみましたが、まだまだいくらでもあります。
これらは「莫」を無指代詞とすれば、都合の悪い例になります。
しかし、都合が悪くとも、例は例です。
戦国時代からすでに見られる用法で、しかも相当数にのぼります。
これについては、私も以前考えたことがあります。
「莫」は「日が草に隠れて見えなくなる」が原義の字で、人や事物の存在を否定する無指代詞としての用法は、その引申義です。
その意味で、用法が無指代詞に限定されるものなのかどうかは、そもそも疑わしいと言えるかもしれません。
また、「無」と「莫」は上古音が近いそうですから、「莫」が「無」の意味で用いられることもあったのではないかとも思います。
一方で、解恵全が『古書虚詞通解』(中華書局2008)で、おもしろいことを述べています。
「莫」を「無」に同じとする諸説に対して、
此项诸例“莫”均出现“莫……者”结构中,“莫”也是无定代词做主语,“……者”做谓语,构成判断句。由于“莫”和“者”在指人这一点上语义重叠,“莫”可译成动词无。
(この項の諸例「莫」は、ひとしく「莫……者」構造の中に現れ、「莫」も無定代詞が主語で、「……者」も謂語であり、判断文を構成する。「莫」と「者」が人を指す点で語義が重なっており、「莫」は動詞「無」と訳せる。)
最後のくだりの訳にちょっと自信がないのですが、要するに、「存在しないものが、~しないものだ」という判断文だというのでしょう。
つまり、「莫不為之惨者」の例なら、「存在しないものがこれのために痛ましく思わないものだ」ということになります。
これは一つの見解ですが、多少無理を感じないではありません。
私は「無」と同義で用いられていると考える方が自然だと思うのですが、いかがでしょうか。
いずれにしても、「莫――者」は、決して用例の少ない形式ではありません。
私なら、このような用法もあると、受験生に紹介しておきたいところです。
なぜなら、「莫」を無指代詞として教える立場にあって、それと矛盾する形式なのですから、ひと言あって然るべきだと思うからです。
SNSなどというものとは縁の遠い生活をしておりまして、ツイッターというものも利用したことがないのですが、たまたま「莫」について調べていると、S氏のツイートを拝見することができました。
S氏は、ずいぶん前にネット上で知り合うことのできた方で、漢文に造詣が深く、仕事の上でもお世話になったことがあります。
そのまま引用するのは憚られますので、端折って載せますと、
「無・莫・勿・毋」は体言を否定するという漢文解説を見たが、「無」はまだしも、「莫」は本当に体言を否定するのか?
というものでした。
「『無・莫・勿・毋』は体言を否定する」という説明がもしなされているのだとしたら、S氏ならずとも驚いてしまいますが、S氏の「『無』はまだしも、『莫』は本当に体言を否定するのか?」という言葉にこめられた意図は、おそらく「無人」のように、「無」の後に体言が置かれることはあっても、「莫人」のように体言が置かれることなどあるのか?ということだと思います。
「無」は「有」の対義で、「~を無す」(=~が存在しない)を肯定的に述べる動詞で、「無人」なら、「人を無す」(=人がいない)という事実を肯定的に判断して述べるものです。
したがって、「無人」は否定文ではなく肯定文になるわけですが、それはともかくとしても、「人」という体言(の存在)を否定していると、言えば言えないこともありません。
ですが、「莫」は中国の語法学では無指代詞(指すもののない代詞)とされ、いわば英語の「nobody」「nothing」に相当すると言われていますから、主語として用いられて、「莫A」の形をとるなら、Aは動詞、もしくは動詞のように働いている語でなければなりません。
つまり、「莫A」は、「存在しないものがAする」から「誰もAしない」または「何ものもAしない」という意味を表すとされるわけです。
「莫」を無指代詞とすることについては、本当にそれが妥当であるかどうか、さらに考える必要はあると思いますが、S氏の「『莫』は本当に体言を否定するのか?」という疑いは、今の説明からも当然のことになります。
ところが、S氏は、さらにツイートされていて、
「莫――者」という表現があることを確認した。しかし用例はわずかで標準的な表現とは言えず、受験に必要な知識ではない。
という旨のことを述べられました。
この時、私は「あれ?」と思ったのです。
「用例がわずか」で「標準的な表現とは言えない」が、気になりました。
S氏が「莫――者」の用例を確認されたのは、「――者」が名詞句になるからでしょう。
「――者」は名詞句ではあっても、体言ではないのですから、そこまでこだわられなくてもいいと思うのですが、ひっかかるところがおありだったのでしょうか。
私が「あれ?」と思ったのは、「莫――者」という表現が結構よく出てくるという認識をもっていたからです。
拙著を改訂していて、「莫」の用法については、多くの用例にあたっていますが、よく目にするような気がします。
試しに自前のデータのgrep検索で「莫.*者。」の例を探してみると、たちまち何百例もヒットしました。
「莫.*者、」やその他の検索を加えれば、相当数にのぼるでしょう。
もちろん単純にこの文字列にヒットした数ですから、一つひとつ吟味すれば除外されるものも多く含まれていると思いますが、「用例がわずか」とはとてもいえません。
・自制河以東、蒼梧已北、莫不厭若魚者。(荘子・外物)
((捕らえた魚のあまりの大きさに、)制河から以東、蒼梧山から以北は、だれもこの魚に食べ飽きないものはいなかった。)
・女倚柱而嘯、旁人聞之、莫不為之惨者。(列女伝・仁智)
(むすめが柱にもたれて口笛を吹くと、そばにいる人はそれを聞き、だれもこの悲しげな音色に痛ましく思わない者はなかった。)
・群臣莫敢諫者。(劉向新序・刺奢)
(群臣たちは諫めようとするものはいなかった。)
古い例をいくつか拾い上げてみましたが、まだまだいくらでもあります。
これらは「莫」を無指代詞とすれば、都合の悪い例になります。
しかし、都合が悪くとも、例は例です。
戦国時代からすでに見られる用法で、しかも相当数にのぼります。
これについては、私も以前考えたことがあります。
「莫」は「日が草に隠れて見えなくなる」が原義の字で、人や事物の存在を否定する無指代詞としての用法は、その引申義です。
その意味で、用法が無指代詞に限定されるものなのかどうかは、そもそも疑わしいと言えるかもしれません。
また、「無」と「莫」は上古音が近いそうですから、「莫」が「無」の意味で用いられることもあったのではないかとも思います。
一方で、解恵全が『古書虚詞通解』(中華書局2008)で、おもしろいことを述べています。
「莫」を「無」に同じとする諸説に対して、
此项诸例“莫”均出现“莫……者”结构中,“莫”也是无定代词做主语,“……者”做谓语,构成判断句。由于“莫”和“者”在指人这一点上语义重叠,“莫”可译成动词无。
(この項の諸例「莫」は、ひとしく「莫……者」構造の中に現れ、「莫」も無定代詞が主語で、「……者」も謂語であり、判断文を構成する。「莫」と「者」が人を指す点で語義が重なっており、「莫」は動詞「無」と訳せる。)
最後のくだりの訳にちょっと自信がないのですが、要するに、「存在しないものが、~しないものだ」という判断文だというのでしょう。
つまり、「莫不為之惨者」の例なら、「存在しないものがこれのために痛ましく思わないものだ」ということになります。
これは一つの見解ですが、多少無理を感じないではありません。
私は「無」と同義で用いられていると考える方が自然だと思うのですが、いかがでしょうか。
いずれにしても、「莫――者」は、決して用例の少ない形式ではありません。
私なら、このような用法もあると、受験生に紹介しておきたいところです。
なぜなら、「莫」を無指代詞として教える立場にあって、それと矛盾する形式なのですから、ひと言あって然るべきだと思うからです。