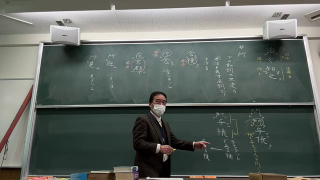「既」は「とても」や「すべて」「すぐに」という意味を表すか?・5
- 2023/11/09 07:49
- カテゴリー:漢文の語法
(内容:「既」が多義語として、「とても」「すべて」「まもなく・やがて・すぐに」などの意味を表すとする説を考察する。その5)
『古代汉语虚词词典(最新修订版)』が挙げている「既」の用法として、最後に次のものを見てみましょう。
五、表示动作行为不久就发生、出现。可译为“不久”。
(動作行為がまもなく発生、出現することを表す。「まもなく」と訳せる。)
前の「四、表示后一动作行为紧接前一动作行为发生、出现。可译为“就”“马上”等。」(後の動作行為が前の動作行為にすぐ引き続いて発生、出現することを表す。「すぐに」などと訳せる。)とどう異なるのだろう?時間の短長だろうか?と思ったのですが。
・既、夫人将使公田孟諸而殺之。(春秋左氏伝・文公16年)
――不久,襄夫人准备让宋昭公去孟诸打猎而杀掉他。
(まもなく、襄夫人は宋昭公を孟諸に狩猟に行かせて彼を殺してしまおうとした。)
どうもこの例は、これまでの「既」の例とは違います。
これまでは、主語の動作行為の完了・終結を示す形で用いられていたのに対して、この例の「既」は「夫人」の動作行為「使公田孟諸而殺之」の完了・終結を表していません。
例文の前を補ってみます。
・宋公子鮑礼於国人。宋飢、竭其粟而貸之。年自七十以上、無不饋詒也、時加羞珍異。無日不数於六卿之門、国之才人無不事也、親自桓以下、無不恤也。公子鮑美而艶。襄夫人欲通之、而不可。乃夫人助之施。昭公無道、国人奉公子鮑以因夫人。於是華元為右師、公孫友為左師、華耦為司馬、鱗驩為司徒、蕩意諸為司城、公子朝為司寇。
初、司城蕩卒。公孫寿辞司城、請使意諸為之。既而告人曰、「君無道、吾官近、懼及焉。棄官則族無所庇。子身之弐也。姑紓死焉。雖亡子、猶不亡族。」
既、夫人将使公田孟諸而殺之。
(▼宋の公子鮑(はう)国人に礼あり。宋飢うるに、其の粟を竭(つ)くして之に貸す。年七十より以上、饋詒せざるは無く、時に珍異を加へ羞(すす)む。日として六卿の門を数(しばしば)せざるは無く、国の才人には事(つか)へざるは無く、親は桓より以下、恤(あはれ)まざるは無きなり。公子鮑は美にして艶なり。襄夫人之に通ぜんと欲すれども、可(き)かず。乃ち夫人之に施を助く。昭公は無道にして、国人公子鮑を奉じて以て夫人に因る。是に於て華元右師たり、公孫友左師たり、華耦(くわぐう)司馬たり、鱗驩(りんくわん)司徒たり、蕩意諸(たういしよ)司城たり、公子朝司寇たり。
初め、司城蕩卒す。公孫寿司城を辞し、意諸をして之たらしめんと請ふ。既にして人に告げて曰はく、「君は無道にして、吾が官近く、焉(これ)に及ばんことを懼(おそ)る。官を棄つれば則ち族庇(おほ)ふ所無し。子は身の弐なり。姑(しばら)く死を紓(ゆる)べん。子を亡ふと雖も、猶ほ族を亡はざらん。」と。
既にして、夫人将に公をして孟諸に田(かり)せしめて之を殺さんとす。)
(▽宋の公子鮑は国の人々に対して礼があった。宋の国が飢饉の際には、その穀物を出し尽くしてかれらに貸し、七十歳以上の老人にはすべて食べ物を贈り、時には珍しいものを加えてすすめた。六卿の門をしばしば訪問しない日はなく、国の賢者には仕えないことはなく、親族は桓公の代以下、情けをかけぬものはなかった。公子鮑は美男子で華やかであった。襄公の夫人は彼に言い寄ろうとしたが、受け付けなかった。そこで夫人は彼に施す面で助けた。昭公は無道であったから、国の人々は公子鮑を奉じて夫人に頼った。この時、華元は右師であり、公孫友は左師であり、華耦は司馬であり、鱗驩は司徒であり、蕩意諸は司城であり、公子朝は司寇であった。
(これより)初め、司城蕩が亡くなった。公孫寿は(その後任の)司城となることを辞退して、(子の)意諸に司城とならせることを求めた。[既而]、人に告げたことには、「わが君は無道であり、私の官位は(君に)近く(高いから)、(災いが)私に及ぶことが心配だ。(かといって)官を捨てれば一族をまもるものがない。子は親の身がわりだ。(わが子を司城にすることで)しばらく死を伸ばせるだろう。子を失っても、(私がいれば)なお一族を失いはすまい。」と。
[既]、襄公の夫人は昭公に孟諸で狩猟させてこれを殺そうとした。)
長い引用になりましたが、例文の中に「既而」と「既」が出てきます。
私は、この2つは同じ意味、同じ用法として用いられていると思います。
まず最初の「既而」は、公孫寿が自ら司城となることを辞退し、我が子の意諸を司城に推薦したという事実が述べられ、いわば「そんなことがあって後」ぐらいの意味で「既而」が用いられ、裏話が述べられます。
次に2つめ、すなわちもとの例文の「既」は、前段で、公子鮑が国人に奉じられ、無道の昭公を排し、襄公の夫人に頼って次の君主にしようという動きがあること、その時点での昭公の家臣達の位置づけが述べられ、意諸が司城になったいきさつには裏話があることが述べられ、やはり「そんなことがあって後」ぐらいの意味で「既」が用いられ、襄公の夫人が昭公暗殺を企んだことが述べられます。
ここで、意諸が司城になったいきさつが挟まっているのは、実はこの後、昭公は結果的に殺されますが、意諸は父の予想通り死んでしまうことになるからです。
私は、これらの「既」は、「既有之、」(既に之有りて~、)そんな漢文があるかどうかわかりませんが、それぐらいの意味で用いられているのではないかと思うのです。
もっというなら、「既」は単独でそれだけの意味をもたされているとも。
「既而」は、「そんなことがすでにあって、して」です。
「既而」の形をとってその意味を表すのではない、「既」がすでにその働きをしているのではないでしょうか。
この場合の「既」が、前段で述べられた内容の完了・終結を表す以上、その後どれぐらいの時間で次の事件が起こるかについては、定まりません。
すぐに起こることもあるでしょうし、それよりはもう少し時間を要して「やがて」ぐらいの感じで発生することもあるでしょう。
つまり、「既」が「すぐに」「まもなく」という意味を表すのではなく、完了・終結した事件と、新たに起こる事件との間に要する時間に委ねられるのではないでしょうか。
『古代漢語虚詞詞典(最新修訂版)』には、この用法として、もう1つ例文が挙げられています。
・予之詩、始学江西諸君子、既又学後山五字律。(楊万里・誠斎荊渓集自序)
――我的诗,起初学江西诗派各位名家,不久又学陈师道的五言律诗。
(私の詩は、初め江西詩派の名家たちに学び、まもなくさらに陳師道の五言律詩に学んだ。)
この例文は、続きがあります。
・予之詩、始学江西諸君子、既又学後山五字律、既又学半山老人七字絶句、晩乃学絶句於唐人。
(▼予の詩は、始め江西の諸君子に学び、既に又後山の五字律に学び、既に又半山老人の七字絶句に学び、晩く乃ち絶句を唐人に学ぶ。)
(▽私の詩は、最初江西の諸君子に学び、[既]さらに後山の五言律詩に学び、[既]半山老人の七言絶句に学び、最後は絶句を唐人に学んだ。)
楊万里が自らの詩作の修行を振り返って述べたものです。
確かに2つの「既」を「まもなく」とか「しばらくして」と訳せば、文意は自然に通ります。
しかし、これは楊万里の修行の段階を示していて、江西の諸君子に学ぶという段階を完了し「そのことが済んで」、次に後山の五言律詩を学んだ。
そしてそれが完了して「そのことが済んで」、さらに半山老人の七言絶句に学んだということではないでしょうか。
前の修得の後、どれぐらいの時間が経過したかまでは「既」は請け負わない、「すぐ」の場合もあるでしょうし、「しばらく経って」からの場合もあるでしょう。
「既」や「既而」が、「すぐに」「まもなく」「やがて」と時間に幅をもたせた形で訳されるのは、実はそもそも「既」が完了・終結を意味して、その後の経過時間を請け負わないからなのではないでしょうか。
さて、検証にあるいは誤りがあるかもしれませんが、私は「既」は色々に訳され、あたかも多義語のように見えるけれども、実は根は1つで、完了・終結で説明ができる語だと思います。
その上で、一番最初の疑問、『史記』刺客列伝の2つの「既」の意味を考えてみましょう。
・軻既取図奏之。(史記・刺客列伝)
(▼軻既にして図を取りて之を奏す。)
(▽荊軻は[既]地図を受け取り(秦王に)差し上げた。)
これが「荊軻はすぐに地図を取って(秦王に)差し上げた」と解されることがあるのですが、果たして本当にそういう意味でしょうか。
暴論かもしれませんが、それなら「軻即取図奏之。」と「即」を用いて表現すればよいことです。
司馬遷はそれを「既」を用いて表現した。
この文は実は、
・軻既取図、奏之。
のように見るべきではないでしょうか。
荊軻は趙人徐夫人の匕首を地図の中にしこんでいました。
今、その地図は震えて使い物にならない秦舞陽のもつ柙(箱)の中にあります。
その地図の入った箱をそのまま秦王に献上してしまうのではなく、地図を秦王の目の前で広げる、あるいは広げさせる必要があった。
そのためには、荊軻は地図そのものを手にとって、その上で秦王に献上する必要があった。
ここまでは私の想像ですが、何にせよ、荊軻は「地図を手に取ってから」すなわち、手にとるという動作行為を完了した上で、それを秦王に献上した。
私はこの「既」をそのように解釈します。
次に、
・於是左右既前殺軻。秦王不怡者良久。(史記・刺客列伝)
(▼是に於いて左右既に前(すす)みて軻を殺す。秦王怡(よろこ)ばざる者(こと)良(やや)久し。)
(▽そこで秦王の側近の者たちが[既]進み出て荊軻を殺した。秦王はしばらくの間不機嫌であった。)
この文も、教科書各社ともこのように句読されていますが、実は、
・於是左右既前殺軻、秦王不怡者良久。
のように、2句を続けて、前の動作の完了を受けて、秦王の状況が述べられる。
つまり、「そこで左右がすでに進み出て荊軻を殺してしまってからも、秦王の不機嫌はしばらく続いた」と見てはいかがでしょう。
側近の荊軻殺害が完了しての、秦王の状況が述べられている、私にはそう思えるのです。
『古代汉语虚词词典(最新修订版)』が挙げている「既」の用法として、最後に次のものを見てみましょう。
五、表示动作行为不久就发生、出现。可译为“不久”。
(動作行為がまもなく発生、出現することを表す。「まもなく」と訳せる。)
前の「四、表示后一动作行为紧接前一动作行为发生、出现。可译为“就”“马上”等。」(後の動作行為が前の動作行為にすぐ引き続いて発生、出現することを表す。「すぐに」などと訳せる。)とどう異なるのだろう?時間の短長だろうか?と思ったのですが。
・既、夫人将使公田孟諸而殺之。(春秋左氏伝・文公16年)
――不久,襄夫人准备让宋昭公去孟诸打猎而杀掉他。
(まもなく、襄夫人は宋昭公を孟諸に狩猟に行かせて彼を殺してしまおうとした。)
どうもこの例は、これまでの「既」の例とは違います。
これまでは、主語の動作行為の完了・終結を示す形で用いられていたのに対して、この例の「既」は「夫人」の動作行為「使公田孟諸而殺之」の完了・終結を表していません。
例文の前を補ってみます。
・宋公子鮑礼於国人。宋飢、竭其粟而貸之。年自七十以上、無不饋詒也、時加羞珍異。無日不数於六卿之門、国之才人無不事也、親自桓以下、無不恤也。公子鮑美而艶。襄夫人欲通之、而不可。乃夫人助之施。昭公無道、国人奉公子鮑以因夫人。於是華元為右師、公孫友為左師、華耦為司馬、鱗驩為司徒、蕩意諸為司城、公子朝為司寇。
初、司城蕩卒。公孫寿辞司城、請使意諸為之。既而告人曰、「君無道、吾官近、懼及焉。棄官則族無所庇。子身之弐也。姑紓死焉。雖亡子、猶不亡族。」
既、夫人将使公田孟諸而殺之。
(▼宋の公子鮑(はう)国人に礼あり。宋飢うるに、其の粟を竭(つ)くして之に貸す。年七十より以上、饋詒せざるは無く、時に珍異を加へ羞(すす)む。日として六卿の門を数(しばしば)せざるは無く、国の才人には事(つか)へざるは無く、親は桓より以下、恤(あはれ)まざるは無きなり。公子鮑は美にして艶なり。襄夫人之に通ぜんと欲すれども、可(き)かず。乃ち夫人之に施を助く。昭公は無道にして、国人公子鮑を奉じて以て夫人に因る。是に於て華元右師たり、公孫友左師たり、華耦(くわぐう)司馬たり、鱗驩(りんくわん)司徒たり、蕩意諸(たういしよ)司城たり、公子朝司寇たり。
初め、司城蕩卒す。公孫寿司城を辞し、意諸をして之たらしめんと請ふ。既にして人に告げて曰はく、「君は無道にして、吾が官近く、焉(これ)に及ばんことを懼(おそ)る。官を棄つれば則ち族庇(おほ)ふ所無し。子は身の弐なり。姑(しばら)く死を紓(ゆる)べん。子を亡ふと雖も、猶ほ族を亡はざらん。」と。
既にして、夫人将に公をして孟諸に田(かり)せしめて之を殺さんとす。)
(▽宋の公子鮑は国の人々に対して礼があった。宋の国が飢饉の際には、その穀物を出し尽くしてかれらに貸し、七十歳以上の老人にはすべて食べ物を贈り、時には珍しいものを加えてすすめた。六卿の門をしばしば訪問しない日はなく、国の賢者には仕えないことはなく、親族は桓公の代以下、情けをかけぬものはなかった。公子鮑は美男子で華やかであった。襄公の夫人は彼に言い寄ろうとしたが、受け付けなかった。そこで夫人は彼に施す面で助けた。昭公は無道であったから、国の人々は公子鮑を奉じて夫人に頼った。この時、華元は右師であり、公孫友は左師であり、華耦は司馬であり、鱗驩は司徒であり、蕩意諸は司城であり、公子朝は司寇であった。
(これより)初め、司城蕩が亡くなった。公孫寿は(その後任の)司城となることを辞退して、(子の)意諸に司城とならせることを求めた。[既而]、人に告げたことには、「わが君は無道であり、私の官位は(君に)近く(高いから)、(災いが)私に及ぶことが心配だ。(かといって)官を捨てれば一族をまもるものがない。子は親の身がわりだ。(わが子を司城にすることで)しばらく死を伸ばせるだろう。子を失っても、(私がいれば)なお一族を失いはすまい。」と。
[既]、襄公の夫人は昭公に孟諸で狩猟させてこれを殺そうとした。)
長い引用になりましたが、例文の中に「既而」と「既」が出てきます。
私は、この2つは同じ意味、同じ用法として用いられていると思います。
まず最初の「既而」は、公孫寿が自ら司城となることを辞退し、我が子の意諸を司城に推薦したという事実が述べられ、いわば「そんなことがあって後」ぐらいの意味で「既而」が用いられ、裏話が述べられます。
次に2つめ、すなわちもとの例文の「既」は、前段で、公子鮑が国人に奉じられ、無道の昭公を排し、襄公の夫人に頼って次の君主にしようという動きがあること、その時点での昭公の家臣達の位置づけが述べられ、意諸が司城になったいきさつには裏話があることが述べられ、やはり「そんなことがあって後」ぐらいの意味で「既」が用いられ、襄公の夫人が昭公暗殺を企んだことが述べられます。
ここで、意諸が司城になったいきさつが挟まっているのは、実はこの後、昭公は結果的に殺されますが、意諸は父の予想通り死んでしまうことになるからです。
私は、これらの「既」は、「既有之、」(既に之有りて~、)そんな漢文があるかどうかわかりませんが、それぐらいの意味で用いられているのではないかと思うのです。
もっというなら、「既」は単独でそれだけの意味をもたされているとも。
「既而」は、「そんなことがすでにあって、して」です。
「既而」の形をとってその意味を表すのではない、「既」がすでにその働きをしているのではないでしょうか。
この場合の「既」が、前段で述べられた内容の完了・終結を表す以上、その後どれぐらいの時間で次の事件が起こるかについては、定まりません。
すぐに起こることもあるでしょうし、それよりはもう少し時間を要して「やがて」ぐらいの感じで発生することもあるでしょう。
つまり、「既」が「すぐに」「まもなく」という意味を表すのではなく、完了・終結した事件と、新たに起こる事件との間に要する時間に委ねられるのではないでしょうか。
『古代漢語虚詞詞典(最新修訂版)』には、この用法として、もう1つ例文が挙げられています。
・予之詩、始学江西諸君子、既又学後山五字律。(楊万里・誠斎荊渓集自序)
――我的诗,起初学江西诗派各位名家,不久又学陈师道的五言律诗。
(私の詩は、初め江西詩派の名家たちに学び、まもなくさらに陳師道の五言律詩に学んだ。)
この例文は、続きがあります。
・予之詩、始学江西諸君子、既又学後山五字律、既又学半山老人七字絶句、晩乃学絶句於唐人。
(▼予の詩は、始め江西の諸君子に学び、既に又後山の五字律に学び、既に又半山老人の七字絶句に学び、晩く乃ち絶句を唐人に学ぶ。)
(▽私の詩は、最初江西の諸君子に学び、[既]さらに後山の五言律詩に学び、[既]半山老人の七言絶句に学び、最後は絶句を唐人に学んだ。)
楊万里が自らの詩作の修行を振り返って述べたものです。
確かに2つの「既」を「まもなく」とか「しばらくして」と訳せば、文意は自然に通ります。
しかし、これは楊万里の修行の段階を示していて、江西の諸君子に学ぶという段階を完了し「そのことが済んで」、次に後山の五言律詩を学んだ。
そしてそれが完了して「そのことが済んで」、さらに半山老人の七言絶句に学んだということではないでしょうか。
前の修得の後、どれぐらいの時間が経過したかまでは「既」は請け負わない、「すぐ」の場合もあるでしょうし、「しばらく経って」からの場合もあるでしょう。
「既」や「既而」が、「すぐに」「まもなく」「やがて」と時間に幅をもたせた形で訳されるのは、実はそもそも「既」が完了・終結を意味して、その後の経過時間を請け負わないからなのではないでしょうか。
さて、検証にあるいは誤りがあるかもしれませんが、私は「既」は色々に訳され、あたかも多義語のように見えるけれども、実は根は1つで、完了・終結で説明ができる語だと思います。
その上で、一番最初の疑問、『史記』刺客列伝の2つの「既」の意味を考えてみましょう。
・軻既取図奏之。(史記・刺客列伝)
(▼軻既にして図を取りて之を奏す。)
(▽荊軻は[既]地図を受け取り(秦王に)差し上げた。)
これが「荊軻はすぐに地図を取って(秦王に)差し上げた」と解されることがあるのですが、果たして本当にそういう意味でしょうか。
暴論かもしれませんが、それなら「軻即取図奏之。」と「即」を用いて表現すればよいことです。
司馬遷はそれを「既」を用いて表現した。
この文は実は、
・軻既取図、奏之。
のように見るべきではないでしょうか。
荊軻は趙人徐夫人の匕首を地図の中にしこんでいました。
今、その地図は震えて使い物にならない秦舞陽のもつ柙(箱)の中にあります。
その地図の入った箱をそのまま秦王に献上してしまうのではなく、地図を秦王の目の前で広げる、あるいは広げさせる必要があった。
そのためには、荊軻は地図そのものを手にとって、その上で秦王に献上する必要があった。
ここまでは私の想像ですが、何にせよ、荊軻は「地図を手に取ってから」すなわち、手にとるという動作行為を完了した上で、それを秦王に献上した。
私はこの「既」をそのように解釈します。
次に、
・於是左右既前殺軻。秦王不怡者良久。(史記・刺客列伝)
(▼是に於いて左右既に前(すす)みて軻を殺す。秦王怡(よろこ)ばざる者(こと)良(やや)久し。)
(▽そこで秦王の側近の者たちが[既]進み出て荊軻を殺した。秦王はしばらくの間不機嫌であった。)
この文も、教科書各社ともこのように句読されていますが、実は、
・於是左右既前殺軻、秦王不怡者良久。
のように、2句を続けて、前の動作の完了を受けて、秦王の状況が述べられる。
つまり、「そこで左右がすでに進み出て荊軻を殺してしまってからも、秦王の不機嫌はしばらく続いた」と見てはいかがでしょう。
側近の荊軻殺害が完了しての、秦王の状況が述べられている、私にはそう思えるのです。