漢文学びのとびら
漢文の学習や、漢文の文法についての情報を発信すると共に、拙著『真に理解する漢文法』、『ためぐち漢文』を無料提供しています。
お勧めの漢和辞典・字源辞典(大学生・教員・一般の方 対象)
(内容:大学生や教員が漢文を学習する上での辞書・字源辞典を紹介。)漢文を読み解く力をつけたい大学生や高等学校の先生方、その他一般の方へ、お勧めの漢和辞典や字源辞典を紹介します。
■漢和辞典
ハンディタイプの漢和辞典については、高校生対象のページで紹介しましたので、そちらをご参照ください。
しかし、本格的に漢文を学ぼうという方は、ハンディタイプの漢和辞典だけでは物足りないとお思いでしょう。
そこで、できれば持っているとよいと思える中型、大型の辞書を紹介します。
1.『学研 漢和大辞典』〔藤堂明保 編〕
(学習研究社)
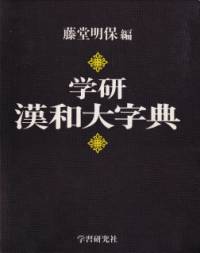
漢字語源学の権威のお一人、藤堂明保氏によるもの。
1978年刊行で古いのですが藤堂語源学を知ることのできる良書です。
漢字を系統的に分類して、丁寧に説明しています。
古書だと500円ぐらいで手に入ります、もったいなすぎてびっくりです。
落合淳思氏によれば、古いがゆえに誤りもあるという藤堂氏の語源研究ですが、それを考慮に入れても、素晴らしい辞書です。
2.『大漢語林』〔鎌田正/米山寅太郎〕
(大修館書店1992)

親字1万4千字、熟語10万語を誇る辞書です。
1冊の中に漢字・漢語の情報を最大限に盛り込んだとのこと。
これも、古書だと3,000円もしません(実にもったいない)。
他にも『講談社新大字典』(講談社)があり、これも1990年代のものですが良書です。
3.『漢語大詞典』全12巻、索引1巻〔漢語大詞典編輯委員会・漢語大詞典編纂処編纂〕
(漢語大詞典出版社)
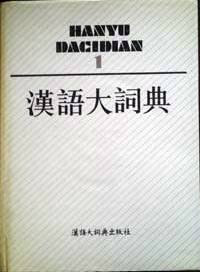
1986年から1994年に上海辞書出版社から出版された、中国というより現在における世界最高の漢語字典です。
親字2万2千、収録語は37万5千語に達するという充実ぶりです。
ただし、もちろん中国語、早い話が最高の中中辞典ですね。
まじめに漢文に取り組もうという学生や先生方は絶対もっていたほうがよい。
唯一の難点はこれだけだと漢字を探しにくいことです。
4.『大漢和辞典 修訂版』全15巻〔諸橋轍次 著〕
(大修館書店)
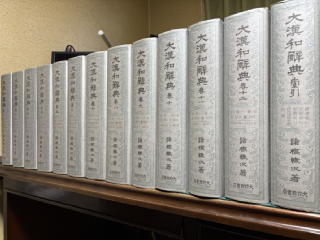
漢文を学ぶ大学生以上でこの辞書を知らない人はいないでしょう。
諸橋轍次氏が生涯をかけて編纂した日本が誇る漢和辞典です。
所載熟語は50万語以上にも及び、中国が「漢語大詞典」を世に出すまでは押しも押されもせぬ世界一の漢和辞典でした。
管理人も大学時代には、この辞書群と寝起きを共にする毎日であったといって言い過ぎではないでしょう。
ただ、漢和辞典の機能というより、むしろ典拠探しに利用する方が多かったのを覚えています。
また、版を重ねるごとに少なくなってはきましたが、引用や訓読の誤りも見られるので、「大漢和辞典に載っていました」の一言は禁句です。
原典にあたる作業が本当はそこから始まるのです。
とはいえ、あまりにも偉大な辞書です。
この辞書を軽視する人は、先人の功績を顧みない人というべきでしょう。
■字源を調べる辞典
最初に断っておきますが、字源研究はどんどん新事実をきわめているので、既存の書籍に述べられていることが誤りだと判明することは当然のことです。
そのあたりの事情は、落合淳思氏の『漢字の成り立ち 『説文解字』から最先端の研究まで』(筑摩書房2014)に詳しく述べられています。
ここでは、現在入手できる漢字の語源に関する辞典を紹介しますが、1つの書物に書かれていることを鵜呑みにするのではなく、複数の書物にあたって、妥当なところを探るという形で管理人は利用しています。
そういうことで、それぞれの書物の性質は落合淳思氏の『漢字の成り立ち』に譲り、ここでは書名だけを紹介します。
1.『漢字の起原』〔加藤常賢〕
(角川書店1970)

2.『漢字語源辞典』〔藤堂明保〕
(学燈社1965)

3.『字統』〔白川静〕
(平凡社1984)
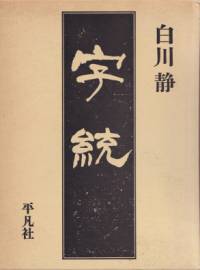
4.『字源』〔李学勤:主編〕
(天津古籍出版社2012)
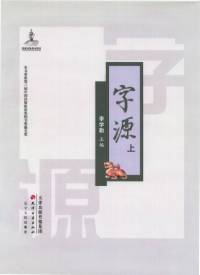
5.『甲骨文字小字典』〔落合淳思〕
(筑摩書房2011)

管理人は、漢字の働きや用いられ方を考えるにあたって、なるべく漢字の元々の語義に基づいて考えるようにしています。
文脈からこのように解釈できるからという理由で、漢字にそのような意味があるのだと決めつけることは危険だと思うからです。
漢字の語源については、ずぶの素人ですが、慎重に漢字の働きを考えたいという思いから、複数の書籍を見比べながら、妥当なところに基づいて考えるようにしています。
なお、落合淳思氏の「漢字の成り立ち 『説文解字』から最先端の研究まで」(筑摩書房2014)は、字源研究の流れや、加藤・藤堂・白川 各氏の研究姿勢、問題点などをわかりやすく述べてあるので、参考になります。
