漢文学びのとびら
漢文の学習や、漢文の文法についての情報を発信すると共に、拙著『真に理解する漢文法』、『ためぐち漢文』を無料提供しています。
真に理解する漢文法/第3部 句式編
(内容:無料提供『真に理解する漢文法』の「第3部 句式編」の詳細を目次で紹介)『真に理解する漢文法』の第3部「句式編」の詳細をご紹介します。
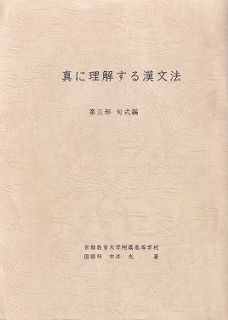
以下に、目次を掲載しますので、参考にしてください。
第三部 句式編
第一章 使役
1.使役を表す動詞を用いる兼語式の文
①使役の動詞「使・令・俾」を用いる形
②具体的な使役動作を表す動詞「勧・命・遣」などを用いる形
2.動詞・形容詞・名詞の使動用法
①他動詞が使役を表す文(他動詞の使動用法)
②名詞・形容詞・自動詞が使役を表す文(名詞・形容詞・自動詞の使動用法)
③その他の使役を表す文
第二章 受身
1.受身を表す助動詞「被・見」を用いる形
◇「る・らる」と読む「見」の特殊用法
2.受身の動作主を表す前置詞を用いる形
①前置詞「被」を用いる形
②前置詞「於・于・乎」を用いる形
3.動詞「為」を用いる受身の形
①「A為BC」の形
②「A為B所C」の形
◇「為~所~」の「為」は動詞か前置詞か?
◇受身では訳しにくい「A為B所C」
◇「A為B所C」の別の読み方
4.主語が受事主語であるため受身になる形
①官位の任免を表す場合
②その他の場合
第三章 否定
1.否定を表す副詞を用いる形
①否定の副詞「不・弗」の用法
◇「弗」と「不」の違い
◇単独で用いられる「不」
◇文末で単独に用いられて選択疑問を表す「不」
②否定の副詞「非・匪」の用法
③否定の副詞「未」の用法
◇会話中で単独に用いられる「未也」
◇文末で用いられる「未」
④否定の副詞「否」の用法
◇文末で単独に用いられて疑問を表す「否」
⑤その他の否定の副詞とされる語
2.存在や所有の否定を表す動詞「無」を用いる形
◇「無以~」の形
3.無指代詞「莫」を用いる形
◇「莫」はなぜ無指代詞なのか?
4.不可能を表す形
5.「不敢A」「無敢A」の形
6.部分否定の形
◇必須を否定する「不必A」の用法
◇「復不A」の形について
7.二重否定の形
①否定の語を連続して二重否定を表す形
ア、結果的に強い肯定を表す二重否定の形
イ、別の事情があることを示す二重否定の形
②助動詞を伴う二重否定の形
◇「ずんばあらず」という読みについて
③副詞を伴う二重否定の形
④兼語文による二重否定の形
8.否定の接続詞「無~」「亡~」を用いて無条件の成立を表す形
第四章 禁止(教戒・否定の命令願望)
1.禁止を表す副詞を用いる形
2.「不可」を用いて禁止を表す形
第五章 疑問
1.疑問の語気詞を用いる形
①単独で用いて判断を求める形
②否定の副詞と共に用いて推測の語気を表す形
◇「君不見」「君不聞」の形
③選択疑問の語気を表す形
④疑問代詞と共に用いて疑問の語気を表す形
2.疑問代詞を用いる形
①疑問代詞「何」の用法
ア、「何」を単独で用いる形
イ、「何」を名詞と共に用いる形
ウ、「何」を前置詞と共に用いる形
◇「何為」の「為」は前置詞か?
◇「何為者」と「何謂者」について
エ、「何」を動詞と共に用いる形
a.「何如・何若・何似」の用法
b.「如何・若何・奈何・謂何」の用法
◇「如之何」「奈之何」はなぜこの語順をとるか?
◇「如何」などを用いて手段・方法がないことを
表す表現
◇「何如・何若」と「如何・若何」の違い
②疑問代詞「誰」の用法
ア、「誰」を単独で用いる形
イ、「誰」を前置詞と共に用いる形
ウ、「誰」を名詞と共に用いる形
エ、「誰何」の形
③疑問代詞「孰」の用法
④疑問代詞「安」の用法
◇疑問代詞「何」「安」が構造助詞「所」を伴う形
⑤疑問代詞「焉」の用法
⑥その他の疑問代詞
3.数詞「幾」を用いて疑問を表す形
4.その他の疑問を表す形
①疑問を表す兼詞を用いる形
②推測疑問を表す「豈」を用いる形
③文末に「不・否・未」を置いて選択疑問を表す形
④「何A之B」の形(「何A」が述語Bの目的語)
⑤「何A之B(也)」の形(AとBが主述、述補関係)
ア、AとBが主述関係の場合
イ、AとBが述補関係の場合
⑥「何其A(也)」の形
第六章 反語
1.反語の語気詞を用いる形
①可能の助動詞や否定を表す語と共に用いる形
②「得無A乎」「得非A乎」の形
③「非A乎」「不A乎」の形
④「君不見」「君不聞」の形
2.反語の語気を表す副詞を用いる形
◇反語を表す副詞「独」について
◇反語以外の意味を表す「其A乎」
3.疑問代詞を用いる形
4.注意すべき反語の形
①「何A為」「何以A為」の形
◇「何A為」の「為」は疑問・反語の語気詞か?
②「何A之B」の形
ア、「何A」が述語Bの目的語である形
イ、A・Bが主述関係である形
③「何其A(也)」の形
④「何必A」の形
⑤「誰A者」「孰A者」の形
⑥「盍A」「盍不A」「何不A」の形
第七章 限定
1.範囲を表す副詞を用いる形
◇「ひたすら・ただただ・かまわずに」の意を表す副詞「但・第・弟」
◇相手への願望を表す「唯・惟」
◇接続詞のように働く「顧」
2.語気詞を用いる形
◇「耳」は推量の語気を表すか?
第八章 累加
1.限定文を否定して累加を表す形
①複文の前半で用いられる形
◇累加の形特有の読み「ただに」
②複文の後半で用いられる形
③単独で用いられて言外の意味を類推させる形
2.限定文の反語で累加を表す形
◇否定形の累加と反語形の累加は同趣旨
第九章 抑揚
1.後文に接続詞「況」を用い、省略表現する抑揚の形
◇「況於・況乎」の「於・乎」
2.後文に「安・豈」などを用いて表現する抑揚の形
3.その他の抑揚の形
①後文の「況」の後を省略しない形
②後文に「況」も「安・豈」も用いない形
③譲歩の接続詞「雖」を用いる形
第十章 仮定(譲歩)
1.「もし~すれば・ならば」という意味を表す仮定の形(仮定表現)
①単音節の接続詞「如・若・苟」などを用いる仮定の形
②副詞から転じた接続詞を用いる仮定の形
ア、語気を表す副詞から転じた仮定の接続詞
イ、時間を表す副詞から転じた仮定の接続詞
ウ、否定を表す副詞から転じた仮定の接続詞
エ、「自非~」の形
◇「自非~」の「自」は仮定の接続詞か?
③使役の動詞から転じた接続詞を用いる仮定の形
④仮定を表す複音節の接続詞
2.「たとえ~(しても・であっても)」という意味を表す仮定の形(譲歩表現)
①「たとヒ」と読む接続詞を用いる譲歩の形
◇「たとひ」という読みについて
②接続詞「雖」を用いる仮定の譲歩の形
◇「いへども」という読みについて
3.文脈から判断して仮定(譲歩)に解する形
第十一章 比況
1.「如・若」などを用いて比況を表す形
①「如・若」などが述語として用いられる形
◇「ごとし」と「ごとくなり」
②「如・若」が状態補語として用いられる形
③「如・若」を用いる固定的な形式
2.「如・若」などを用いて推測を表す形
3.「ごとし」「ごとくす」と読む「如・若」を用いるその他の形
①「従う」の意の「如」
②話題を転じる接続詞としての「如・若」
第十二章 異同
1.形容詞+「於」前置詞句で異同を表す形
2.「与」前置詞句+形容詞で異同を表す形
第十三章 比較
1.「如・若」を用いて比較を表す形
①「不如・不若」を用いて二者を比較する形
◇選択を表す「不如・不若」
②無指代詞「莫」や動詞「無」と、「如・若」を併せ用いて、比較の最上級を表す形
◇見かけ上「莫如」「無如」の形をとる、比較とは異なる形式
2.前置詞「於」などを用いて比較を表す形
①形容詞述語+「於」前置詞句で比較を表す形
②無指代詞「莫」+形容詞述語+「於」前置詞句で比較の最上級を表す形
第十四章 選択
1.二者の選択を検討する形
①「AでなければBである」という選択的判断を示す形
②「Aか、Bか」「AにするかBにするか」などの選択的疑問を示す形
③「寧」や「其」を用いて「Aにしようか、Bにしようか」という選択的疑問を示す形
2.二者の一方の選択を自分で主張、または相手に求める形
①二者の前者を選ぶ前提の形
②二者の後者を選ぶ前提の形
第十五章 感嘆・詠嘆
1.嘆詞を用いる形
2.感嘆・詠嘆を表す語気詞を用いる形
3.疑問や反語を用いる形
①疑問の形式で感嘆・詠嘆を表す形
②反語の形式で感嘆・詠嘆を表す形
第十六章 希望・願望
1.希望・願望の意の動詞を用いる形
2.希望・願望の意の助動詞や副詞を用いる形
◇時間副詞「欲」との違い
◇「他者への希望」と「自分の希望」の形式の違い
◇推量・推測の意味を表す「庶・庶幾・庶乎」
3.反語を用いて希望・願望を表す形
◇反語を表す「安得~」の形
◇疑問を表す「安得~」の形
第十七章 原因・理由
1.前置詞を用いて原因・理由を表す形
①原因・理由を表す前置詞句が連用修飾句として述部を
修飾する形
②原因理由を表す前置詞句が述部になる形
2.接続詞を用いて原因・理由を表す形
◇読みを誤りやすい「故」
◇「是以」と「以是」の違い
3.「所以」を用いて原因・理由を表す形
①「所以」句が主語になる形
◇理由とは別の意味で用いられる「所為・所謂」
②「所以」句が述語になる形
◇原因・理由以外の意味を表す「所以」句
③「所以」句が目的語になる形
④「所以」が結果を表す接続詞である場合
4.構造助詞「者」を用いて原因・理由を表す形
5.「何則・何者・何也」を用いて原因・理由を表す形
◇「何則・何者」の「則・者」は疑問の語気詞か?
第十八章 推量・推測
1.副詞を用いて推量・推測を表す形
①副詞「蓋・或・意・恐・殆」等を用いて推量・推測を表す形
◇「けだし」という読みについて
◇推量以外の意味を表す「蓋」
②「其~乎」が推量・推測を表す形
③副詞「庶・庶幾」を用いて推量・推測を表す形
④「如・若」を用いて推量・推測を表す形
2.反語表現で推量・推測を表す形
①「不A乎」「非A乎」の形
②「豈A哉」「豈有A哉」の形
③「得無A乎」「得非A乎」の形
④「無乃A乎」の形
第十九章 倒置
1.主述文における述語の倒置
2.述語構造における目的語の倒置
◇「此之謂也」「此之謂乎」の形
3.連体修飾語の倒置
4.疑問・反語に伴う目的語の倒置
①目的語が疑問代詞で述語に倒置される形
②前置詞の目的語が疑問代詞で倒置される形
③「何A之B」「何A之有」「何A之為」の形
5.否定文における代詞目的語の倒置
①否定の副詞を用いる否定文における代詞目的語の倒置
◇「不知我」と「不我知」の違いは?
②動詞「無」を用いる否定文における代詞目的語の倒置
③無指代詞「莫」を用いる否定文における代詞目的語の倒置
④助動詞や副詞を伴う否定文における代詞目的語の倒置
◇訓読上の倒置
後記
参考文献
句形索引
用語・漢字索引
以上が、『真に理解する漢文法』第3部 句式編のご紹介です。
ご参考までに。
PDFファイルをご希望の方は、こちらをご覧ください。